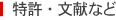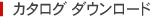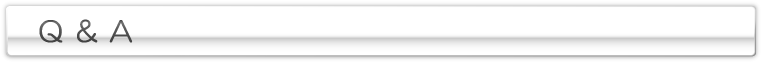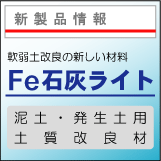よくあるご質問
| 材料に関すること |
2. Fe石灰処理土とはどういうものですか?
3. 粒調Fe処理材とはどういうものですか?
4. 各材料の購入方法は?
5. 六価クロム溶出量の確認は必要ですか?
6. Fe石灰処理土の設計強度は?
7. Fe石灰処理土・粒調Fe処理材の保管できる期間は?
8. Fe石灰による周辺の農作物への影響はありますか?
9. Fe石灰・Fe石灰処理土の色が違うのはなぜですか?
| 出来高・品質管理に関すること |
2. Fe石灰技術研究所が実施する品質管理(CBR)費はいくら?
3. Fe石灰処理土や粒調Fe処理材のロス率(土量変化率)は?
4. 現場密度試験の規格値(基準値)は?
| 施工に関すること |
2. 転圧回数は?
3. 1層あたりの施工厚は?
4. 転圧していたらクラックが発生しました。その場合どうしたらよいですか?
5. Fe石灰工法の1日あたりの施工量はどのくらいですか?
6. 雨の日の施工はできますか?また、急に雨が降ってきた時の対応は?
7. Fe石灰処理土面、粒調Fe処理材面での交通開放は可能ですか?
よくあるご質問の答え
| 材料に関すること |
| Q1. | Fe石灰とはどういうものですか? |
| A | Fe石灰とは、消石灰に微粉酸化鉄を混合した土質安定材(地盤改良材)です。 荷姿は、750kg(フレコンパック)、バラ(ジェットパック車)の2種類です。 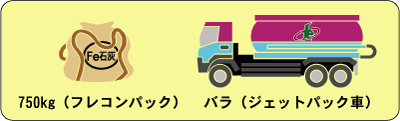 |
| Q2. | Fe石灰処理土とはどういうものですか? |
| A | Fe石灰処理土とは、Fe石灰と良質土(主にまさ土、地域によってはシラスや土丹など)を混合した路床改良(補強)材です。 Fe石灰処理土は、高い耐水性と耐久性の舗装基盤を構築する材料です。 |
| Q3. | 粒調Fe処理材とはどういうものですか? |
| A | 粒調Fe処理材とは、Fe石灰処理土の用度に骨材40%~60%を混合し粒度を調整した路盤材(地域によってはFe石灰処理土と同一の場合がある)です。 粒調Fe処理材は、Fe石灰処理土の特性を生かしながら、施工直後でも路盤材として必要な強度(初期耐荷力)を確保できます。 |
| Q4. | 各材料の購入方法は? |
| A | Fe石灰は、(株)エフイ石灰工業所が製造、(株)ニッシンなどが販売しています。 Fe石灰処理土や粒調Fe処理材は、九州各県にあるFe石灰系処理材製造業者(Fe石灰混合プラント)が製造・販売しています。 詳細については、弊社までお問い合わせください。 |
| Q5. | 六価クロム溶出量の確認は必要ですか? |
| A | Fe石灰は、六価クロム溶出試験を行う必要はありません。六価クロム溶出試験はセメントを含有成分とする固化剤について実施することが義務づけられています。 Fe石灰にはセメント成分は含まれていません。 |
| Q6. | Fe石灰処理土の設計強度は? |
| A | 各地域ごとに標準の設計強度が設定されています。 これはFe石灰処理土の強度が混合する用土の性状(地域性)により異なるためです。詳細については、発注者または弊社にお問い合わせください。 |
| Q7. | Fe石灰処理土・粒調Fe処理材の保管できる期間は? |
| A | 原則として3日間です。製造されたFe石灰処理土はすみやかに現場に搬入し、敷きならし転圧をしなければなりません。 |
| Q8. | Fe石灰による周辺の農作物への影響はありますか? |
| A | 農作物への影響はありません。Fe石灰の主原料は農業用肥料(土壌改良材)に用いられる石灰と根腐れを防ぐ酸化鉄です。 ただし、現地混合の場合は、作物の開花時にFe石灰が付着すると受粉の妨げになるため、この時期の施工には注意が必要です。 |
| Q9. | Fe石灰・Fe石灰処理土の色が違うのはなぜですか? |
| A | Fe石灰の主成分である酸化鉄は、原料に鉄鉱石が用いられています。鉄鉱石は種類や産地によって色が異なることから、Fe石灰やFe石灰処理土にも色の差異が現れます。ただし、成分や品質には問題ありません。 |
| 出来高・品質管理に関すること |
| Q1. | Fe石灰の品質管理を具体的に教えてほしい | |||||||||||||||
| A | 品質管理の項目と、品質管理を実施する機関、実施基準は以下の表の通りとなります。
詳細につきましては弊社までお問い合わせください。 |
| Q2. | Fe石灰技術研究所が実施する品質管理(CBR)費はいくら? | ||||||||||||
| A | Fe石灰工法は化学反応を活用した特殊工法であることから、工事1件ごとに本工法実施および品質管理(CBR試験)費が必要です。 なお、品質管理費については以下の表をご参考ください。
|
| Q3. | Fe石灰処理土や粒調Fe処理材のロス率(土量変化率)は? |
| A | ロス率については、「配合試験結果報告書」(材料承認願)の下段「Ⅲ.Fe石灰処理土の配合」の示方配合欄に記載しています。 まさ土を用土に用いる場合、Fe石灰処理土のロス率は1.41(損失率5%を加算)、粒調Fe処理材では1.33が標準です。なお、まさ土以外の用土を用いる場合は、特に注意してご確認ください。 |
| Q4. | 現場密度試験の規格値(基準値)は? |
| A | 現場密度基準値は、「配合試験結果報告書」に記載している[基準値]に準拠してください。 規格値については当サイトの「どこに使うの?」の各種「管理」のページをご参照ください。 |
| 施工に関すること |
| Q1. | Fe石灰工法の施工手順を教えてほしい |
| A | 施工方法は主に3種類に分類され、「中央混合方式」「路上混合方式」「構造物基礎」があります。 「中央混合方式」の施工方法は、軟弱路床の一部と混合プラントで製造されたFe石灰処理土を置き換える方法で、床堀り→不陸整正→搬入→敷均し→転圧の拘泥で行います。 なお、詳細については当サイトの「どこに使うの?-道路舗装-施工手順」のページをご参照ください。 「路上混合方式」については、在来路床とFe石灰をスタビライザなどで現地混合処理する方式で、Fe石灰の配列→散布→混合→敷きならし→転圧の工程で行います。 この路上混合方式は、混合による材料の均質性の低下や粉じんなどによる環境問題が生じるため、原則として交通量の少ない「農道」に適用されます。 なお、詳細については当サイトの「どこに使うの?-農道舗装-施工手順」のページをご参照ください。 「構造物基礎」については中央混合方式となり、施工方法も同方式と同様になります。 なお、詳細については当サイトの「どこに使うの?-構造物基礎-施工手順」のページをご参照ください。 |
| Q2. | 転圧回数は? |
| A | Fe石灰処理土および粒調Fe処理材の転圧回数はタイヤローラ(8~20t)を使用して7回以上です。 しかし、現地路床土が非常に軟弱で、転圧によって路床が乱される恐れがある場合は、転圧機械を変更して基準密度を確保して下さい。ただし、転圧機械の変更については、発注者の承諾が必要です。 |
| Q3. | 1層あたりの施工厚は? |
| A | Fe石灰処理土の1層当たりの施工厚は、最小8cm、最大20cmです。また、粒調Fe処理材の1層あたりの施工厚は、最小10cm、最大20cmです。 |
| Q4. | 転圧していたらクラックが発生しました。その場合どうしたらよいですか? |
| A | ヘアクラック程度であれば問題ありません。 またそれ以上のクラックが発生し、路床が乱される恐れがある場合は、すみやかに転圧機械を小型のローラなどに変更して下さい。ただし、転圧機械の変更については、発注者の承諾が必要です。 |
| Q5. | Fe石灰工法の1日あたりの施工量はどのくらいですか? |
| A | 打換え工事の場合、一日の施工延長は20~50mを目安としています。ただし、現場状況や施工時間帯によって施工量は異なります。 |
| Q6. | 雨の日の施工はできますか?また、急に雨が降ってきた時の対応は? |
| A | 雨の日の施工は行わないで下さい。水の影響で転圧が効かず所定の密度が得られません。 また、敷きならし作業中に雨が降り始めたときは、敷きならし作業を中止するとともに、敷きならしたFe石灰処理土をすみやかに締め固めて下さい。 |
| Q7. | Fe石灰処理土面、粒調Fe処理材面での交通開放は可能ですか? |
| A | 原則としてFe石灰処理土面、粒調Fe処理材面での交通解放はできません。Fe石灰処理土面、粒調Fe処理材面での交通開放を行うと、走行車両や降雨の影響で、表面の膨張、流出や練り返しの原因となるため、交通開放は、最低5cm程度の粒状路盤を舗設した後としています。 |
その他のご不明な点はお問い合わせ下さい
その他にご不明な点がございましたら弊社へお気軽にご相談下さい。
弊社ではあらゆる状況に対応するため、充実したサポート体制を整えております。
詳細はこちら[サポートページへ]