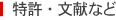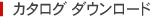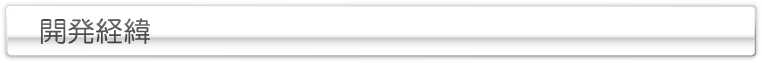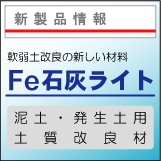『Fe石灰』の開発着眼点
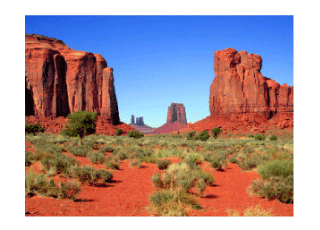 アメリカでは石灰安定処理が広く行われており、高い強度を得られることが知られています(道路,飛行場など)。 これは、金属元素の酸化鉄が集積した土壌である『ラテライト土壌』が広く分布していて、その土壌に対して石灰安定処理の効果が高いためです。
アメリカでは石灰安定処理が広く行われており、高い強度を得られることが知られています(道路,飛行場など)。 これは、金属元素の酸化鉄が集積した土壌である『ラテライト土壌』が広く分布していて、その土壌に対して石灰安定処理の効果が高いためです。
一般の土 :
石灰 + 土中の粘土鉱物 + 水分
ラテライト土:
石灰 + 土中の粘土鉱物 & 金属酸化物 + 水分
↓
日本ではラテライト土の代表として赤土がある
↓
赤土を用いた石灰安定処理を路床改良に適用
『Fe石灰』の開発経緯
創始者「井 月夫」は建設省(現国土交通省)・佐賀国道工事事務所長に赴任し、軟弱な有明粘土が分布する佐賀低平地地帯における国道の修繕工事に苦慮していました。 当時、軟弱地盤対策には現在の路床構築やサンドイッチ舗装工法に通じる方法が採用されていたことから、これをヒントに試行錯誤を繰り返し、アメリカの石灰安定処理に着目してFe石灰工法を開発しました。
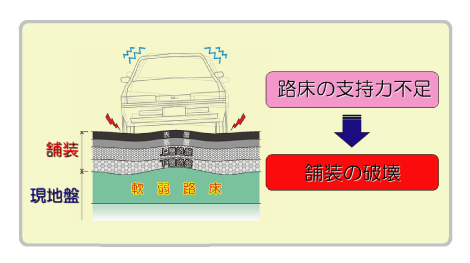
路床に起因した舗装の破壊
舗装は路床の支持力によって維持されています。路床の支持力不足が舗装の破壊の原因となります。
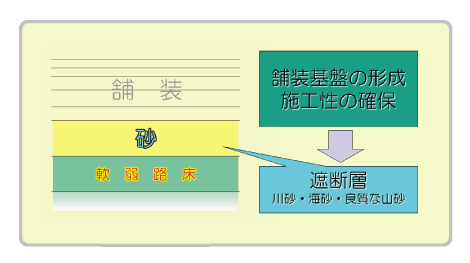
軟弱路床の対策工法
遮断層を設けることで、舗装基盤が構築され施工性が向上します。
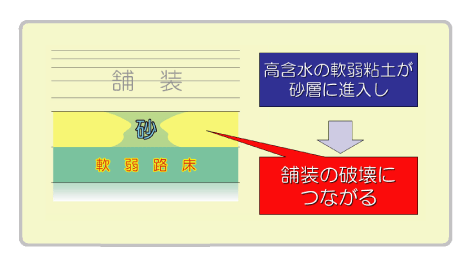
Fe石灰工法の開発起源
しかし、砂層は軟弱土が浸入しやすく、舗装に影響を及ぼしてしまいます。
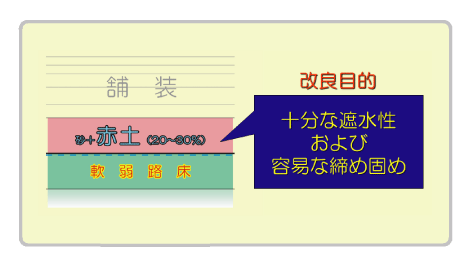
軟弱路床の改良
そこで従来の砂層に赤土を20~30%混合することで、十分な遮水性・容易な締固めが可能となりました。
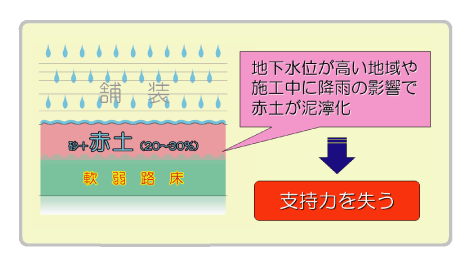
新たなる課題
しかし、地下水位が高い地域や降雨などにより赤土が泥濘化し、支持力を失ってしまいます。
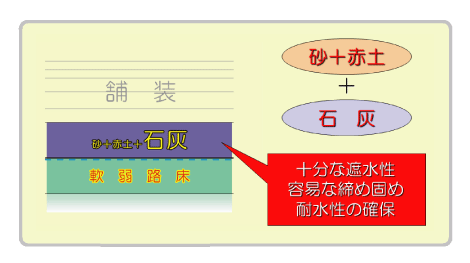
良好な舗装基盤の形成
そこで石灰安定処理することにより、十分な遮水性・容易な締固め・長期にわたる耐水性が確保され、バランスのとれた舗装基盤を構築することが出来ました。
しかし、赤土がどこの地域でも容易に入手出来るわけではない
↓
そこでアメリカにおける赤土(ラテライト土)の石灰安定処理をヒントになぜ有効なのかを検証
↓
赤土に含まれる金属元素(鉄・アルミニウム)が石灰との相性がよいことが判明
↓
その結果を踏まえ、それぞれの材料に含まれる成分に着目し、入手が容易な材料と置き替えた
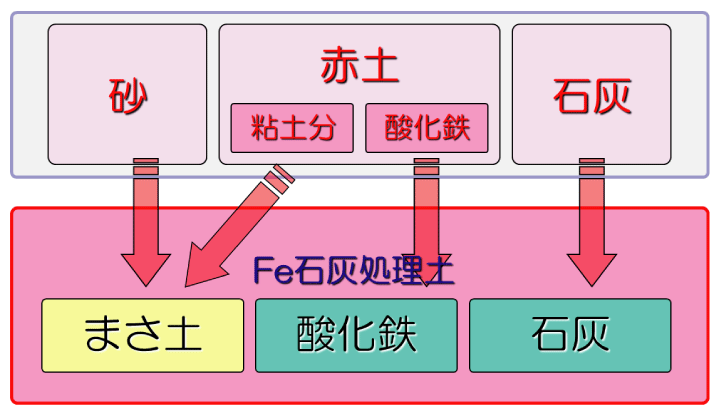
このまさ土に、赤土に含まれる酸化鉄を補足するため、九州では鉄鋼産業が盛んであることから製鉄所から排出される酸化鉄を添加混合し、アメリカの石灰安定処理の原理を人工的に再現したFe石灰処理土が誕生しました。
また、混合場所への提供を容易にするため、石灰に酸化鉄をあらかじめ加えた安定材を製造する方法を採用しました。これがFe石灰安定材です。